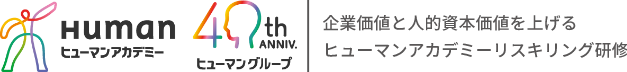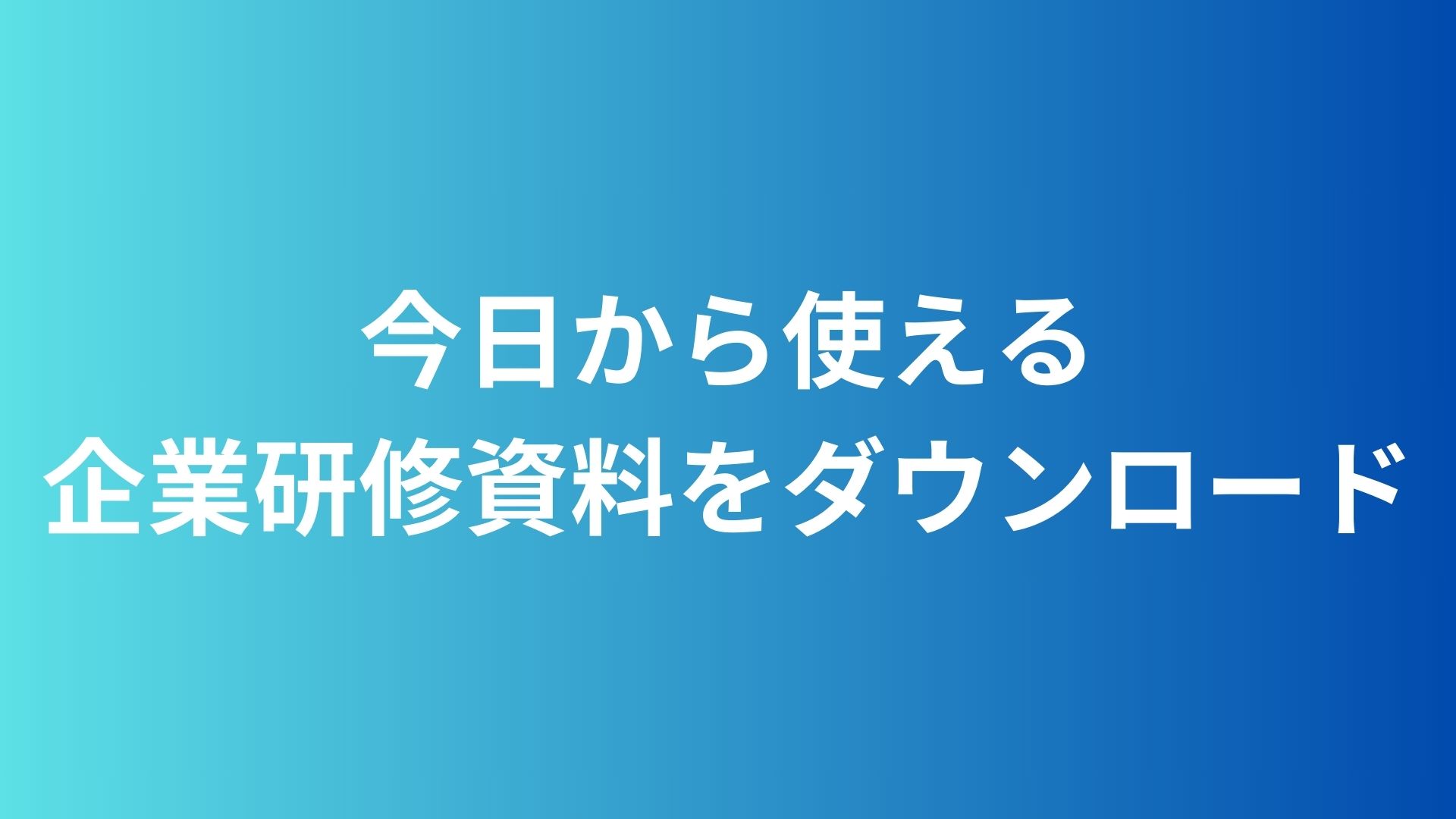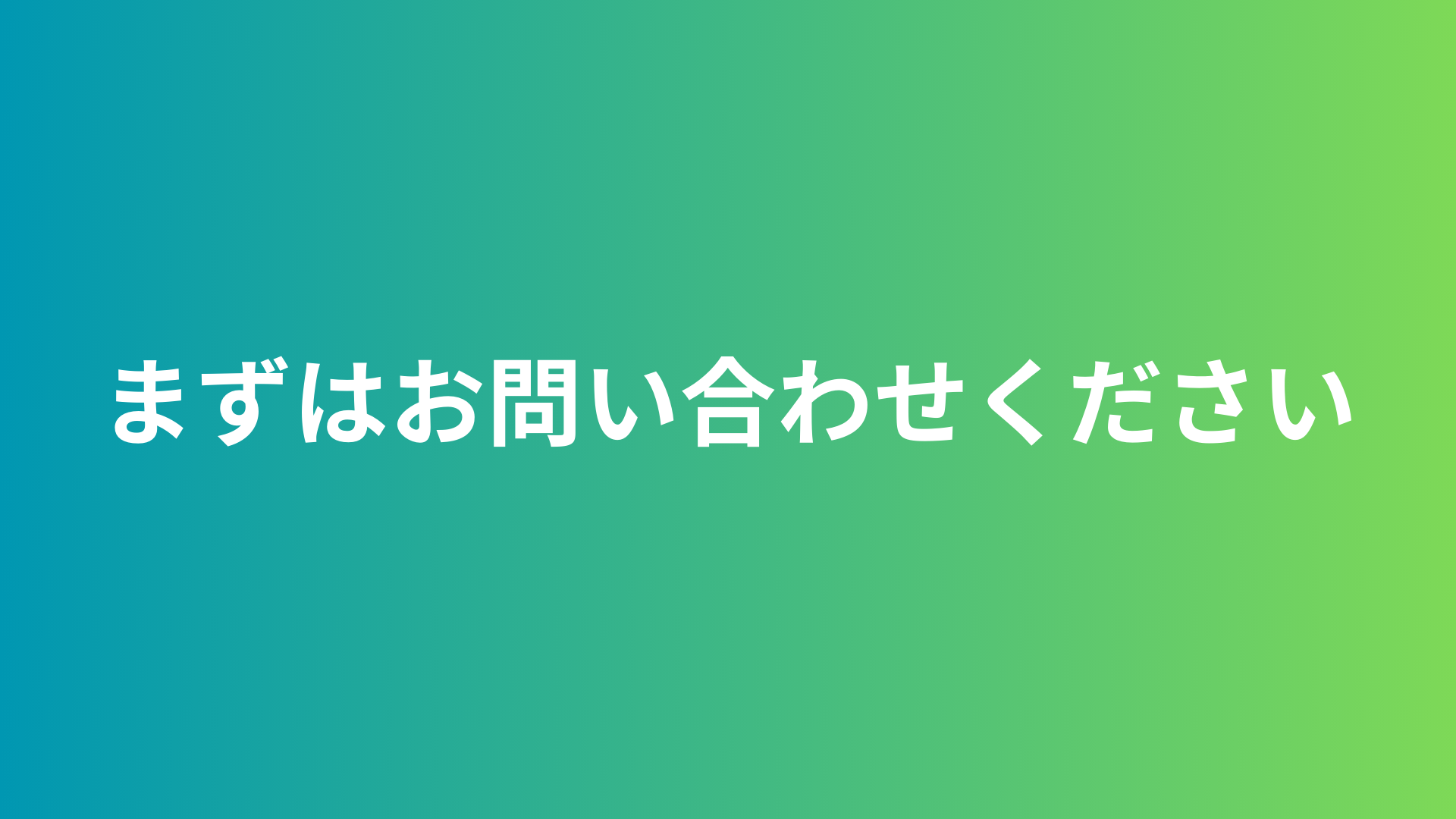MBOは目標管理の代表的な手法で、組織の目標と個人の目標を連動させ自律的な行動を促す仕組みです。
しかし、以下のような課題を感じている方も多いのではないでしょうか。
・MBOの具体的な定義や目的が理解できていない
・OKRやKPIなど他の目標管理手法との違いが分からない
・MBOのメリット・デメリットを把握した上で導入したい
本記事では、MBOの基本的な概念や他の手法との比較、メリットとデメリットについて詳しく解説します。
また、MBOを成功させるためのポイントや実施プロセス、効果測定の方法についても触れているので、MBO導入の検討や運用改善にお役立てください。
人事-研修担当者300名へのアンケート調査
MBOとは?定義と目的
MBOとは、「Management by Objectives」の略で、目標による管理を意味する経営手法です。組織の目標と個人の目標を連動させ、目標達成に向けて自律的に行動することを促す仕組みです。
ここではMBOの定義と目的について詳しく解説するとともに、MBOが重要視されている背景についても触れていきます。MBOを理解することで、組織のパフォーマンス向上と持続的な成長の実現につながるでしょう。
MBOの定義
MBOは、組織の目標と個人の目標を連動させ、目標達成に向けて自律的に行動することを促す経営手法です。組織の上位目標から部門目標、個人目標へとブレイクダウンし、各個人が自らの目標を設定します。
目標設定の際は上司と部下が話し合い、具体的で達成可能な目標を設定することが重要です。
また、目標達成度の評価は上司と部下の面談を通じて、フィードバックを受けながら目標達成に向けて自律的に行動することが求められます。
MBOが重要視されている背景
MBOが重要視されている背景には、組織を取り巻く環境の変化があります。
グローバル化の進展や技術革新のスピードアップにより、組織は常に変化に対応することが求められています。このような環境下では、トップダウンの指示命令型の管理では柔軟な対応が困難です。
そのため、MBOは個人の自律性を重視し、変化に対応する組織づくりを可能にする経営手法として注目されています。また、MBOは個人のモチベーション向上にも効果があり、組織の活力を高めることにもつながるでしょう。
MBOの目的
MBOの目的は、組織の目標達成と個人の成長の両立です。MBOでは、組織の目標と個人の目標を連動させることで、組織全体で目標達成に向けて取り組むことができます。
また、個人の目標設定と達成度の評価を通じて、個人の成長と能力開発も促進されます。MBOは、組織の目標達成と個人の成長を同時に実現することで、組織の持続的な発展を可能にする経営手法と言えるでしょう。
さらに、MBOは組織内のコミュニケーションを活性化するため、上司と部下の信頼関係の構築にも寄与します。
MBOと他の目標管理手法との比較

MBOは目標管理の代表的な手法ですが、近年ではOKRやKPIなど、他の目標管理手法も注目を集めています。それぞれの手法には特徴があり、組織の状況や目的に合わせて選択することが重要です。
ここではMBOと他の代表的な目標管理手法であるOKRとKPIを比較し、その違いを解説します。
OKRとの比較
OKRは「Objectives and Key Results」の略で、目標(Objectives)と重要な結果(Key Results)を設定し、短期間で集中的に取り組む目標管理手法です。MBOが年単位の目標設定が一般的なのに対し、OKRは四半期単位など、より短期の目標設定が特徴です。
また、OKRでは目標の達成度を数値化することを重視します。一方、MBOでは目標の達成プロセスにも焦点を当てるため、定性的な目標も設定されます。
OKRはスピード感のある目標達成に適しているのに対し、MBOは長期的な視点で組織の目標を設定し育成を重視する手法と言えるでしょう。
KPIとの比較
KPIは「Key Performance Indicator」の略で、組織の重要な業績指標を示します。MBOが目標達成のプロセスを重視するのに対し、KPIは結果に焦点を当てます。
KPIは売上高、利益率、顧客満足度など、数値化された指標を用いて設定されるのが一般的です。MBOでは個人の目標設定と評価に重点を置くのに対し、KPIは組織全体の業績評価により重点を置いている点も大きな違いです。
KPIは組織の重要な指標を可視化し、経営判断に活用するのに適した手法である一方、MBOは個人のモチベーション向上と育成により効果を発揮すると言えます。
MBOのメリット・デメリット

MBOは組織の目標達成と個人のモチベーション向上に効果的な目標管理手法ですが、メリットとデメリットの両面を理解することが重要です。
ここではMBOのメリットとデメリットを詳しく解説します。
MBOのメリット
MBOの主なメリットは、以下の通りです。
- 組織全体で目標を共有し、一丸となって目標達成に取り組むことができる。
- 個人の目標設定により、自律的に仕事に取り組むことができ、モチベーションが向上する。
- 上司と部下の間で目標を共有することで、コミュニケーションが活性化する。
- 目標達成のプロセスを重視するため、個人の成長と育成につながる。
MBOを導入することで、組織全体で目標を共有し個人のモチベーションを高めながら、組織の目標達成を目指すことができるでしょう。また、目標達成のプロセスを通じて個人の成長と育成も促進されます。
MBOのデメリット・課題
MBOのデメリットや課題には、以下のようなものがあります。
- 目標設定が難しく、適切な目標を設定するには経験とスキルが必要です。
- 目標の達成度評価の公平性を確保することが難しい場合があります。
- 短期的な目標達成に偏ると、長期的な視点が失われる恐れがあります。
- 個人の目標に偏重すると、組織全体の協力体制が損なわれる可能性があります。
MBOを効果的に機能させるためには、これらのデメリットや課題を認識し、適切に対処することが重要です。目標設定のスキルを向上させ公平な評価制度を確立するとともに、長期的な視点を持ちながら、組織全体の協力体制を維持することが求められます。
MBOを成功させるためのポイント

MBOを導入しても、適切に運用しなければ効果を発揮することができません。MBOを成功させるためには、具体的で達成可能な目標設定、適切なフィードバック体制の整備、形骸化やノルマ化を防ぐ工夫が不可欠です。
ここでは、MBOを効果的に機能させるためのポイントを詳しく解説します。
具体性・難易度のバランスがとれた目標を設定する
MBOで目標を設定する際は、具体性と難易度のバランスが重要です。
目標が抽象的すぎると、達成度の評価が難しくなります。一方、目標が具体的すぎると柔軟性が失われ、変化への対応が困難になります。
また、目標の難易度が高すぎると達成意欲が損なわれ、逆に低すぎると成長の機会が失われてしまいます。
目標設定の際は、これらのバランスを考慮し、適切な目標を設定することが求められます。
フィードバック体制を整備する
MBOでは目標達成のプロセスを重視するため、適切なフィードバック体制の整備が欠かせません。上司と部下が定期的に面談を行い目標の進捗状況を確認するとともに、課題の把握と解決策の検討を行うことが重要です。
フィードバックは部下の成長を促し、目標達成をサポートする重要な機会となります。また、フィードバックを通じて上司と部下のコミュニケーションが活性化することで、信頼関係の構築にもつながるでしょう。
形骸化やノルマ化リスクを防ぐ工夫を取り入れる
MBOを継続的に運用していくと、目標設定が形骸化したりノルマ化したりするリスクがあります。このようなリスクを防ぐためには、MBOの本質的な目的を理解し、適切な運用を行うことが重要です。
目標設定の際は組織の方向性と個人の成長を考慮し、柔軟性を持たせることが求められます。また、評価制度についても過度な数値目標の設定を避け、プロセスを重視した評価を行うことが重要です。
さらに、MBOの運用状況を定期的に見直し、必要に応じて改善を図ることも欠かせません。
MBO(目標管理制度)の実施プロセス

MBOを効果的に運用するためには、一連のプロセスを体系的に実施することが重要です。ここでは、MBOの実施プロセスを5つのステップに分けて解説します。
- 組織目標の設定
- 個人目標への落とし込み
- 行動計画の策定と実行
- 進捗管理とフィードバック
- 評価と次サイクルへの反映
一連の流れを理解することで、MBOを自社に適した形で導入し、定着させることができるでしょう。
①組織目標の設定
組織目標の設定は、MBOの出発点となる重要なステップです。経営陣は自社のビジョンや中長期的な戦略を踏まえ、組織全体で達成すべき目標を明確に定義します。
この目標は、具体的かつ測定可能であることが求められます。また、組織目標は各部門や個人の目標設定の基礎となるため、社内で広く共有し浸透させることが重要です。
②個人目標への落とし込み
個人目標は組織目標と連動しつつ、各個人の役割や責任に応じて設定されます。目標設定の際は、本人の能力や経験、キャリア志向などを考慮し、達成可能な目標を設定することが重要です。
また、目標設定のプロセスで上司と部下が十分にコミュニケーションを取ることで、部下の主体性を引き出し、自発的な目標達成を促すことができます。
③行動計画の策定と実行
個人目標を達成するためには、具体的な行動計画を策定し、実行に移すことが不可欠です。目標達成に必要なタスクやリソースを明確にし、スケジュールや担当範囲を定めます。
計画の実行段階では、日々の進捗状況を把握し、必要に応じて計画の修正を行います。上司は部下の進捗状況を定期的にチェックし、適切なアドバイスやフィードバックを与えることが求められます。
④進捗管理とフィードバック
MBOでは目標達成のプロセスを重視するため、進捗管理とフィードバックが重要な役割を果たします。定期的な報告会やミーティングを通じて計画との差異や課題を分析し、必要な改善策を講じます。
また、管理職やチームメンバーからの適切なフィードバックは、部下のモチベーションを維持・向上させる上で欠かせません。上司は部下の成果を認め、課題解決に向けたサポートを行うことが求められます。
⑤評価と次サイクルへの反映
MBOのサイクルの最後は、評価と次サイクルへの反映です。一定期間ごとに目標の達成度や取り組みのプロセスを評価し、報酬や育成計画に反映します。評価の際は数値的な成果だけでなく、目標達成に向けた努力やプロセスも重視することが大切です。
また、評価結果を踏まえ次のサイクルでより効果的な目標管理を実施できるよう、改善点を洗い出し、体制を整えることが求められます。評価方法については、次の見出しで詳しく解説します。
MBOの導入効果を測定する方法

MBOを導入した後は、その効果を適切に測定し評価することが重要です。
ここでは、MBOの導入効果を多角的に測定し、評価するための方法を具体的に解説していきます。
定量的指標で測定する
MBOの導入効果を測定する上で、定量的な指標は欠かせません。生産性や業績、離職率など、数値化できる指標を用いて評価を行います。
例えば、MBO導入前後の売上高や利益率の変化、一人あたりの生産性の向上度合い、離職率の低下幅などを比較することで、MBOの効果を定量的に把握することができます。
これらの指標は組織の業績に直結するため、MBOの導入効果を測る上で重要な役割を果たします。
定性的指標で測定する
定量的な指標だけでなく、定性的な指標もMBOの導入効果を測定する上で重要です。社員アンケートやヒアリングを通じて、MBO導入後の社員の意識や行動の変化を把握します。
例えば、目標達成に向けたモチベーションの向上度合い、上司と部下のコミュニケーションの活性化、自律的な行動の増加などを評価します。
これらの定性的な指標は数値化は難しいものの、MBOの導入が組織文化や社員のエンゲージメントに与える影響を理解する上で欠かせません。
目標達成度と事業成果の相関分析を行う
MBOの導入効果を総合的に評価するためには、目標達成度と事業成果の相関分析を行うことが有効です。個人の目標達成度と組織全体の業績との関連性を分析することで、MBOが事業成果にどのような影響を与えているかを明らかにします。
例えば、目標達成度の高い部門や個人が、売上高や利益率の向上にどの程度貢献しているかを分析します。
この分析結果を基に、MBOの運用方法の改善や目標設定の見直しを行うことで、より効果的なMBOの運用が可能となります。
まとめ
本記事では、MBO(Management by Objectives)について解説しました。
最後に、記事の内容をおさらいしておきましょう。
- MBOは組織と個人の目標を連動させ、自律的な行動を促す経営手法である。
- MBOは他の目標管理手法(OKR、KPI)と比べ、組織と個人の目標連動に重点を置いている。
- MBOのメリットは組織全体での目標共有、モチベーション向上、コミュニケーション活性化などがある。
- 一方でMBOには目標設定の難しさ、評価の公平性確保、短期的視点への偏重リスクなどのデメリットもある。
- MBOを成功させるには適切な目標設定、フィードバック体制の整備、形骸化やノルマ化の防止などが重要である。
MBOは組織のパフォーマンス向上と持続的成長に有効な経営手法ですが、導入には十分な準備と継続的な改善が必要不可欠です。
自社の状況に合わせて柔軟にMBOを活用し、組織力を高めていきましょう